肉食者鄙(肉食する者は鄙なり)(「墨余録」)
「山の日」を祝う人為的な意味はよくわかりませんが、要するに立秋祭なのであろう。海の日が大暑の至ったことを祝う祭りと思われますので、海の日と山の日の間にうなぎ食っとけ、という国家の思し召しであろう。食いませんけど。秋になってから食います。
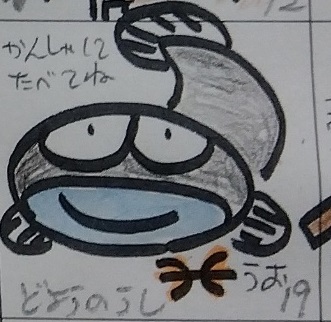
いつまでも黙って食べられてるだけだと思うなよニョロ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あちこち登山してたひとのお話をしましょう。山の実をくれるかも知れません。
清の道光年間といいますからアヘン戦争のころですが、浙江・呉門に眠雲山人というひとがいた。姓は陸氏で、三国呉の大司馬・陸抗の子孫であるという。読書を好み、詩才有り、文章はもっとも世間を驚かせ、しばしば科挙試験を受けたが、
終不合有司尺度、因棄挙子業。
ついに有司の尺度に合わず、因りて挙子の業を棄つ。
とうとう試験官の役人たちの定規では測り切れず、このため官僚を目指す人生を止めてしまった。
「有司の尺度に合わず」はいい言い方ですね。勉強になる。
その後は、
放情於山巓水涯、所歴名山大川不知凡幾。
情を山巓・水涯に放ち、歴するところの名山・大川は凡(およ)そ幾ばくなるかを知らず。
感情を山の頂や水の際に解放するようになり(要するにあちこちを旅するようになった)、これまでに廻った名のある山、大きな川はいったいどれぐらいになるか、わからない。
ある時は、西北の崑崙山脈からチベット、さらにインドに行こうとしたが、途中で路銀が尽きて帰ってきたこともあったという。
こうやって各地を経巡っているうち、わたしとは道光甲辰年(1844)に知り合ったのである。
それ以降、申浦の港を通るときには、必ずわたしの家に寄ってくれるようになった。
毎顧則携山果数筐、分給児輩。
顧するごとにすなわち山果数筐を携え、児輩に分給す。
立ち寄ってくれるときには、いつも山の木の実や果物を数箱手土産に持ってきてくれて、こどもたちに分けてくれるのであった。
子どもたちには、「みんうんおじさん」として大人気でした。
帰時、余無所贈、惟以筆墨報之、而眠雲特喜甚。
帰時、余に贈るところ無く、ただ筆墨を以てこれに報ずるに、眠雲特に喜ぶこと甚だし。
彼が帰っていくとき(完全な放浪者ではなく、呉門に山荘みたいなのがあるんです)に、わたしには贈るものがない。筆と墨を使ったもの、すなわち書と画ぐらいしかないので、それを差し出してみると、眠雲山人は大喜びするのであった。
余曰、人言余画疏落、不求暈飾。君独宝蓄之、何也。
余曰く、人言う、余の画は疏落にして暈飾を求めず、と。君ひとりこれを宝蓄するは何ぞや。
わたしは言った、「世間のひとは、わたしの絵のことを「さっぱりしすぎて飾り気がない」と評している。あなただけがえらく宝物のように集めてくれるのは何故なのか?」と。
眠雲山人が言うには、
子画乃寒畦蔬味、豈足以供肉食者。
子の画はすなわち寒畦の蔬味なり、あに以て肉食する者に供うるに足らんや。
「おまえさんの絵は、なんというか、冬の畑の野菜の味、なんじゃな。豪華な肉料理を食べているやつらの食膳に供えたところで、やつらには何もわからんよ」
やっぱり! そうでしたか! そうですよね!
わたしは言った、
僅如是乎。夫肉食者鄙、固無足算。実告君、余画恰以蔬淡勝、惟如眠雲山人之不火食者、方能賞鑑耳。
僅かにかくの如きか。それ、肉食する者の鄙なる、もとより算うるに足る無し。実に君に告げんに、余の画のあたかも蔬の淡なるを以て勝ること、ただ眠雲山人の火食せざる者の如きのみ、まさに能く賞鑑せん。
「ただそれだけですか。まったく、豪華な肉料理を食っているようなやつらのあさはかな鑑識眼などもともと相手にはしておりません。あなたにだけは申し上げますが、わたしの絵がまるで野菜のように薄い味な点がすぐれていることは、眠雲山人のように火を使った料理をせず果実などだけを食べている方だけが、理解して賞めてくださるのです」
「わははは」「いひひひ」
乃相与大笑而別。
すなわち相ともに大笑して別る。
そこで、二人で大笑いして別れた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
清・毛祥麟「墨余録」巻五より。なんとなく傷をなめ合っているような気もするのですが、二人とも嬉しいんだから、いいか。
それにしても、わたしども肝冷斎派の絵に対する世俗のひとびとの評価が低いのが何故か、ついにわかりました。みなさん、肉を食べなければ肝冷画が好きになりますよ!・・・高齢社会対策で包摂が進めば、こんな話でも聞いてくれるようになるのであろう。ああよかった。
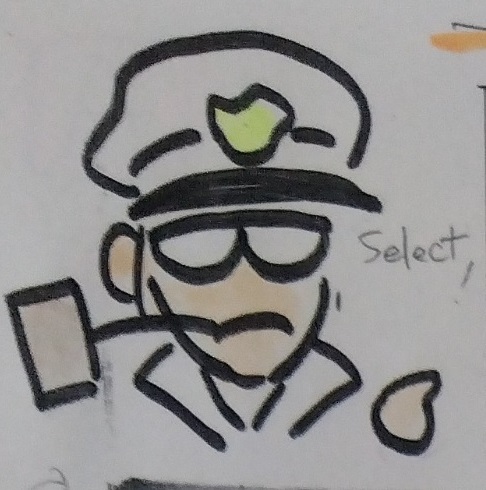
ユーもアメリカンビーフを食べてみな、できれば上か特上をな。
HAHAHAHA!
コメントを残す