化作春泥(化して春泥と作(な)る)(「己亥雑詩」)
あたま痒いです。フケもたくさん出るし、だんだん泥になっていくんだと思います。
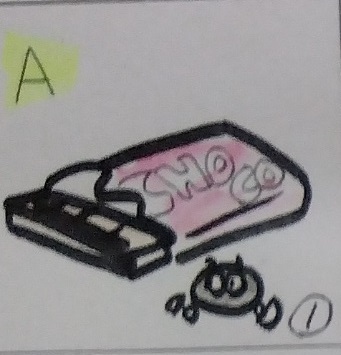
甘いことばかり言っているやつは一般に危険だ。虫歯になったりする。
・・・・・・・・・・・・・・・・
己亥年というのは、道光十九年(1839)、林則徐が大量のアヘンを没収して焼いた年です。翌年、鴉片戦争が勃発する。その年、わたしは北京を出て、郷里の杭州に還ることになった。
詩はもう作らないことにしていたのに、その道中、その誓いを破って作ってしまった。
その一。
著書何似観心賢。不奈巵言夜湧泉。
書を著すは何ぞ観心の賢なるに似ん。巵言(しげん)の夜泉を湧かすを奈(いか)んともせず。
(生きることの意味を考えるなどの目的に対して、)文章を書くという行為は、自分の心を見つめるという行為のすぐれているのに及ばない。
しかし、さかずきに満ちるコトバのように、無意味はコトバが、夜、泉のように湧いて(詩が出)きてしまうのだ(から、しようがないではないか)
「巵」(し)は、さかずきの一種ですが、「巵言」(しげん)と熟するのは「荘子」寓言篇に出る言葉です。荘子は言う、
おれの言葉は、
寓言十九、重言十七、巵言日出。
寓言は十に九、重言は十に七、巵言は日に出づ。
十言ったうちの九は、真理を何かにたとえて言っているのだ。十言ったうちの七は、重大なコトバなのだ。一方、毎日湧いてさかずきに満ちるようなコトバもある。
と言って、それぞれの「言」を解説してくれるのですが、
巵言日出、和以天倪、因以曼衍。所以窮年。不言則斉、斉与言不斉、言与斉不斉也。故曰無言。
巵言は日に出づ、和するに天倪を以てし、因るに曼衍を以てす。年を窮むる所以なり。言わざれば則ち斉(ひと)しく、斉と言は斉しからず、言と斉は斉しからざるなり。故に曰く、言無し、と。
さかずきに満ちて来るコトバ、は毎日毎日湧いてくるのだ。これに天の真理を交えてやり、目的も定めずに続けてやる。そうすると、寿命まで生きることができる。言語にしなければ世界は等質である。世界が等質であることと言語は等質ではない。言語と世界が等質であることも等質ではない。このため、言語は無い、と前から言っているわけだ。・・・
まだまだこんなのがずっと続くので、もうこのへんにしておきます。何か大切なことを言っているに違いない、と思って読んでも、何言っているかわからないと思います。ほんとは大切なことかも知れないんですが、こちらを混乱させることが目的かも知れない。まじめに解釈した方がいいのか、読み飛ばした方がいいのか・・・と混乱させてくるのが「荘子」のやり方ですから気をつけねばなりません。もう放っておいて次に進みましょう。うーん、だが、もしかしたら真理が書いてあるのかも知れないので、他の奴には先に行かせておれだけはマジメに読まなければ・・・。と、「荘子」を読むとこんな感じで混乱してしまいます。
そういうわけでどんどん詩が出来て、
百巻書成南渡歳、先生続集再編年。
百巻の書成るは南渡の歳、先生の続集の再び編まるるの年なり。
百巻(みたいに多い巻数)の詩集が、わたしの南に帰る年に出来てしまった。
(つまり)この年は、わたしの(すでに筆を絶って以前の詩文集はまとめてしまったので)第二の全集が編集されることになるわけだ。
これは全体の序文みたいになっています。
その二。
浩蕩離愁白日斜、吟鞭東指即天涯。
浩蕩(こうとう)たる離愁に白日斜めにして、吟鞭の東指すれば即ち天涯。
広がりたゆたう別れの悲しみの中、太陽は斜めに沈み始めた。
(こうしてはいられないと)詩人(であるわたし)は馬にまたがり、鞭で東の方を指し示した。そこはもう天の果てである。
落紅不是無情物、化作春泥更護花。
落紅はこれ情無きの物ならず、化して春泥と作りてさらに花を護らん。
落ちた赤い花びらは、冷酷な無生物ではないのだ。
春の泥にどろどろと同化して、次に生まれて来る花を(肥料として)支えていくことだろう。
落ちた花が次の花を支えることになる、「化して春泥と作りてさらに花を護らん」―――この一句を、その後の革命の中で多くの志士たちが口ずさむことになろうとは、詩人は全く知らないはず。
・・・・・・・・・・・・・・・
清・龔自珍「己亥雑詩」(「定盦全集」所収)より。このひとは、この「己亥雑詩」を三百十五首作ったんです。今日はその一首目と二首目だけで、もうおしまい。気力も体力も能力も無い。セリーグと一緒で、もうダメになってきたんです。えらいひともみんな泥になっていったのだからいいですけどね。近衛文麿さんは自殺時に54歳だそうです。
コメントを残す