争似作魚閑(いかでか魚となりて閑たるに似ん)(「栖霞閣野乗」)
サカナになってヒマにしていたいなあ。
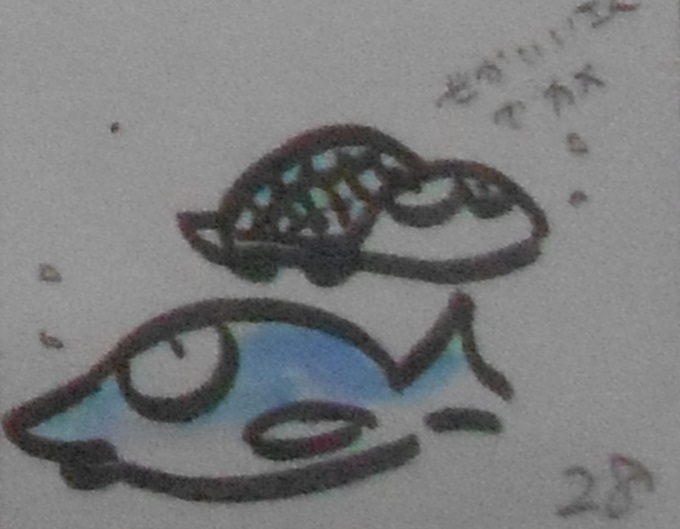
「海の中は生存競争なければのどかでカメ」「ただし、おれもカメもサカナではないでルカ」
・・・・・・・・・・・・・・
清も終わりに近い咸豊年間(1851~61)ごろのことと思いますが、湖南・武昌のひと謝南衡ら数名が四川、雲南の地に探検に出かけ、原住民どもに聖地として怖れられていた洞窟(この地の地名を冠して「大寧洞」と呼ばれていた)に入った。
松明を灯して入って行くと、入り口から数十尺のあたりに、
有一黄冠、兀座如枯枝。
一黄冠有り、兀座して枯枝の如し。
一人の黄冠(道士のことです)が座っていた。まるで枯れた枝のようにじっとしている。
薄暗い松明の光の中で、
「こんにちは」
問之不答。試手触其冠、応手堕地為灰。
これに問うも答えず。試みに手にてその冠に触るるに、応手に地に堕ちて灰と為れり。
声をかけてみたが答えない。どうしたのだろうと、そっと手をかけてみたが、手がその冠に触れた瞬間、冠は地面に落ちて、灰になって崩れた。
ギョギョッ!
それは、座ったままのミイラだったのだ。
もうミイラ化してかなりの時が流れているようである。
傍有一印、文曰大寧巡検司。
傍らに一印有り、文に曰く「大寧巡検司」と。
傍に印鑑が一つ落ちていた。拾い上げて松明の火で印字を読んでみると「大寧巡検司」とある。
一行は顔を見合わせた。
「「巡検司」は明の時代の辺境監督官の職名だな・・・」
「ということは・・・」
蓋此人明世為是官、鼎革後避地修真于此、坐脱。印故所佩、雖入定未嘗舎也。
けだし、この人は明世に是の官為(た)りて、鼎革の後、避地してここに修真し、坐脱す。印はもと佩するところ、入定すといえどもいまだ嘗て舎(す)てざるなり。
つまり、この人は明代にこの官にあったのであろう。清の世の中になって、新しい王朝に仕えることを嫌がって、官署から離れてここで道士となって修行し、ついに座ったまま魂の脱出に成功―――死んだのだ。印鑑は紐が腐敗して落ちた痕跡があり、もともと腰につけていたようである。悟りに入ってミイラ化する時にも、前朝への恩義を忘れずに捨てることなく大切に帯びていたのである。
一行はミイラに深々と拝礼すると、さらに奥に進んだ。
洞深処石壁、有題一絶。
洞の深き処の石壁に一絶を題する有り。
海門千丈浪如山、一転千年瞬息間。洞裡聞雷催雨急。作龍争似作魚閑。
海門千丈の浪、山の如きも、
一転して千年、瞬息の間なり。
洞裡に雷の、雨を催すこと急なるを聞く。
龍と作(な)るは争(いかで)か似ん、魚と作りて閑なるに。
海岸の岩に打ち寄せる波浪は高さ千丈(3000メートル!)、山のようだ。
波は一転して崩れ落ちていく―――それと同じように、千年の月日も一回瞬きし一回呼吸する間のようなものである。
洞窟の外から、カミナリが大急ぎで雨を呼んでいる音が聞こえてきたが、
(雷雨に変じて空に昇っていく)龍になるより、魚になってぼんやりと暮らしている方がよろしいようだ。
もちろん「龍」は功名を争う人生を象徴します。
一行の中で誰かが言った。
「これは明の儒者・羅念庵の詩ではないか」
道流言念庵先生住静処、皆不可知也。
道流言う、念庵先生の住静の処と。みな知るべからざるなり。
道教にかぶれたやつは、羅念庵先生は晩年道教を信仰していて、その最後の修業の地がここだったのではないか、と言うのだが、何事ももう知ることのできない昔のことである。
ただ、ミイラの人が羅念庵の弟子であったとすれば、年代も合わないことはない。
・・・・・・・・・・・・・・・
清・孫静安「栖霞館野乗」より。カミナリが鳴るかのように、韓国は国民ですが、チャイナは政府が怒ってきました。何かあちらの御事情があるのでしょう。対応はみなさんにお任せして、おいらは処理水の中で泳ぐ魚のように楽して生きようっと。しばらく売れないから漁師さんにも獲られないかも知れないし。ホタテ好きなんです。
今日はギョッとするようなえらい人にかっこいい飯食わせてもらいました。昨日までの食生活がウソのようです。