巨万乳下垂(巨万の乳、下垂す)(「弇州山人四部稿」)
題名見てドキドキしたりニヤニヤしてる人はいますか? 肝冷斎はにやにやしながら訳しだしてしまいましたのじゃ。
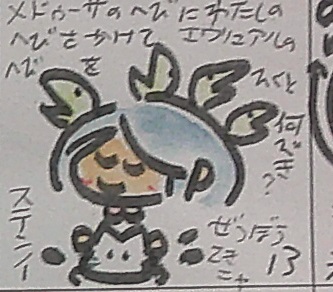
わたしたちゴルゴン族は海底の洞窟の暗闇などに潜んでいて、捕まえたものを食べちゃうのよ、うっふっふー。ネコちゃんは洞窟はきらい?
・・・・・・・・・・・・・・・・
明の時代のことですが、わし(わしは後七子の代表的人物・王世貞じゃ)は江蘇・宜興の東にある東九湖に舟を浮かべた。
一面に湖水は青緑色、両側から山が迫り、湖面には背の高い木々の影と、黄色い雲かと見まがうように実った稲穂が映っていた。特に、夕陽が照らすと、ますます素晴らしい。
湖を渡り切って、湖父といわれる船泊に舫う。
夜過半、忽大雨、滴灑入蓬戸。余起、低回久之、質明始霽。
夜半ばを過ぎて忽ち大雨し、滴灑(てきしゃ)して蓬戸に入る。余起ちて、低回これを久しくし、質明に始めて霽れたり。
夜中過ぎに、突然大雨になった。雨滴が船室の粗末なカーテンから灑ぐように入り込んでくる。わしは起き上がって、しばらくうろうろしていた。明るくなりかけたころに、やっと止んで、晴れてきた。
同行者は、弟の王敬美、山東のひと李くん、安徽のひと程くん、地元の沈くん、張くん。
この時、わしは足を痛めていた(痛風と思われる)。李くんも体調がよくないという。それに敬美が竹かごを持って来ていた。この三人が籠を頼んで、あとの三人が徒歩で上陸。
四里半(2キロ弱)ばかり行ったところで、目指す洞窟に到着した。遠くから見ると、土を放り出して伏せたような丘である。
一行の中で張くんだけが一度来たことがあるという。彼が言うには、手前に見える入口から入ると味気なく見終わってしまう、裏手の入り口から入らなければならない、と。
それでは裏口から入るとどんなふうに素晴らしいのか、と訊くと、「知らない」とのことだった。「知らないからそちらから行こう」というのである。そこでそうすることにした。
みんなで松明を手にして、小さな穴から入り込み、釣り上げられた魚のように一列になって降りる。降りれば降りるほど滑りやすくなってきて、しかも階段が急になってくるので足の置き場がない。両足を引っ付けるようにしてそろそろと降りる。前の人と引っ付いて、肩を借りあって何とか進む。今度は上が狭まってきたので、肩を借り合うわけにも行かなくなる。
こんな風にして百数十段も降りると、
稍稍睹前行人、如烟霧中鳥。又聞若瓮中語者、発炬則大叫驚絶。
稍稍として前行の人を睹るに、烟霧中の鳥の如し。また、瓮中に語る者のごときを聞き、炬を発するに大いに叫び驚絶す。
だんだんと、前を行く人が、霧の中の鳥のように覚束なくなってきた。さっきもそうだったのだが、人の言葉が、甕の中でしゃべっているように聞こえる。「松明を掲げてみろ」と言っているらしいので、掲げてみて―――
うわあーーーー!!!!!
わしらは大声で叫び、驚いて絶句してしまった。
巨万乳皆下垂、崛礧甗錡、玲瓏晶炯、不可名状。
巨万の乳、みな下垂して、崛礧(くつらい)の甗錡(げん・き)、玲瓏晶炯(れいろうしょうけい)として、名状すべからず。
数えきれないほどの鍾乳石が、すべて下に向かって垂れて、飛び出したり丸まったりした「こしき」や「なべ」のような形で、きらきら・ぴかぴかと光り輝いて、言葉で説明できるような状態ではないのだ。
残念でした、垂れていたのは鍾乳石でした。キタイ外れでしたね。
鍾乳石の色は漁陽(北京周辺)でとれる美玉のように青く、しかして潤いを含むところはそれに勝る。西南側に大きな平たい石があり、石の柱がその上にこんもりと立っていて、そのあたりには、「床」「霊薬竈」「塩蔵」などと呼ばれる奇岩がある。東の方に向かってだんだん下がっていき、また湿り気を帯びていく。そちらに行ってみようと移動するとだんだん水が浸みだしてきて、行き止まりになる。このあたりを「仙人の田んぼ」というそうだ。
降りてきた入口を振り返ってみると、はるかな頭の上に、きらきらと太陽の中の影にように、見えたり見えなかったりするのが、それだ。
さらに行くと、通路がほとんど断たれているような場所に着いた。下の方に二尺ばかりの空間があり、そこを匍匐して通り過ぎ、また下ったり上ったりして、
忽呀然中辟、可容万人坐、石乳之下垂者、愈益奇、為五色自然、丹蒦晃爛指人眼。
忽ち呀然として中辟すること、万人の坐するを容るるべし。石乳の下垂するもの、いよいよますます奇、五色を自然に為して、丹蒦(たんかく)、晶蘭として人の眼を指す。
「蒦」(かく)はほんとは「丹」を左につけてください。ウルシを塗った漆器製品のことだそうです。
突然、「あっ」と驚くように目の前が開け、そこには一万人が座れるような広間があった。ここも、鍾乳石が上から垂れ下がり、さっきよりもさらに変化してすばらしい。色はおのずと五色に輝き、まるで赤い漆器の反射光のように、わしらの目を射た。
鍾乳石は、
大者如玉柱、或下垂至地、所不及者尺所、或怒髪上、不及者亦尺所、或上下際不接者僅一髪。
大なるものは玉柱の如く、あるいは下垂して地に至り、及ばざるところ尺所、あるいは怒髪の上るあり、及ばざるものまた尺所、あるいは上下際して接さざるものわずかに一髪なるあり。
大きいのは玉の柱のようで、下に垂れて地面まであと一尺ぐらい、というのもあれば、怒った髪のように下から上がってきて、天井まであと一尺ぐらいというのや、上と下から迫ってきて、引っ付くまであと髪一本だけ、というようなのもある。
石状如潜虬、如躍龍、如奔獅、如踞象、如蓮華、如鐘鼓、如飛仙、如僧胡、詭不可勝紀。
石状は潜虬(せんきゅう)の如く、躍龍の如く、奔獅の如く、踞象の如く、蓮華の如く、鐘鼓の如く、飛仙の如く、僧胡の如く、詭にして紀するに勝(た)えざりき。
形をみれば、淵に潜むみずちのようなの、躍り上がった龍のようなの、走り回るライオンのようなの、うずくまった象のようなの、蓮華のようなの、鐘太鼓のようなの、飛んでいる仙人のようなの、ペルシア人の僧侶のようなの、などなど、変なのばかりで表現しきることができない。
わしはどんどん足が動かなくなってきたが、頑張って上った。広間に突き出したような石の台があって、そこから全貌が見渡せるのだ。これが最後の見せ場だった。酒と料理を持ってきたはずの一人がいないと言って騒いだが、やがてやってきたので、少し飲んで、洞窟から出た。
出たところが、さっき迷った手前からの入り口だった。手前から入ると今の石の台の上に出て、そこで広間を見渡して帰ってくる、だけだったのだ。
さて、この洞窟を「張公洞」という。張公がここに棲んだのでそう名付けられたのだといい、張公というのは、漢の時代の五斗米道を起こした張道陵だ、とも、唐の玄宗皇帝に仕えた仙人の張果老だ、とも言うが、そうではあるまい。張道陵は四川地方のひとだし、ここは仙女が住む金や玉で飾られた宮殿でもなければ、三国志に登場する左元放が集めたような霊芝があるわけでもなかった。
王先生(←わしのことじゃ)曰く、
先ほど目にした石の「床」や「霊薬竈」や「塩蔵」やあと「碁盤」もあったかな、あれらは
彷彿貌之耳。
彷彿としてこれに貌どるのみ。
そのように見えるので、そう名付けているだけじゃ。
烏言仙迹哉、烏言仙迹哉。
いずくんぞ仙迹と言わんや、いずくんぞ仙迹と言わんや。
どうして神仙たちのいた証拠だと言えるだろうか、どうして神仙たちのいた証拠だと言えるだろうか。
そんなものは無いのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・
明・王世貞「游張公洞記」(張公洞に游ぶの記)(「弇州山人四部稿」巻七十二所収)です。全部漢文書いて読み下すと明後日の朝までかかるので原文は一部だけにさせていただきました。ああ、どこか遠くへ行きたいなあ。どこか仙人の棲むようなところへ。だが、王先生の言うとおり、そんなものは無いのだろう。どこにも。