寧至踣乎(なんぞ踣(たお)るるに至らんや)(「近思録」)
うっせい、うっせい、うっせいわ・・・の声も聞こえてきそうである。
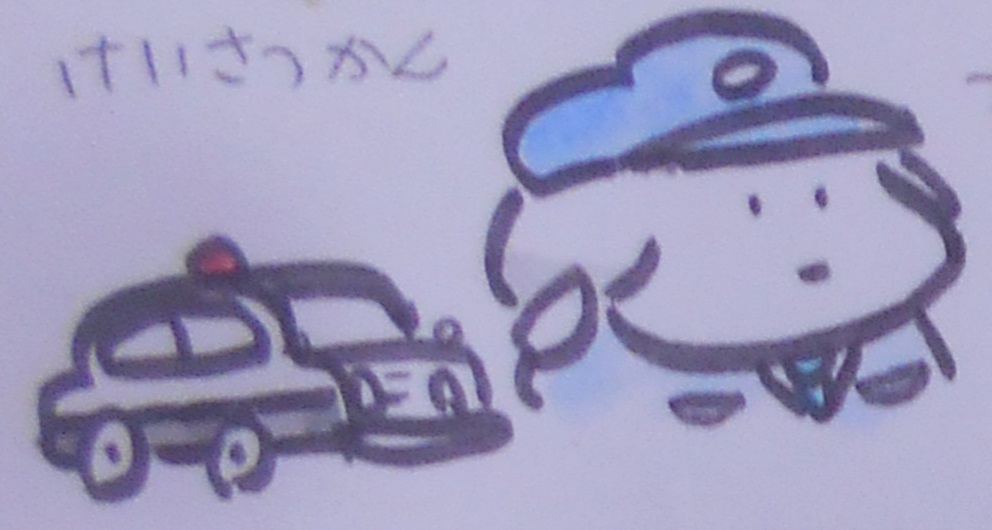
反抗する子どもはつかまえるでワン!
・・・・・・・・・・・・・・・・
北宋の名儒・程伊川先生が死んだおふくろのことについて言っております。
治家有法、不厳而整。不得笞扑奴婢、視小臧獲、如児女。
家を治むるに法有りて、厳ならざるも整えり。奴婢を笞扑(ちぼく)するを得ず、小臧獲を視ること、児女の如し。
家内を切り盛りするのになかなか手馴れておられて、そんなに厳しくは無かったがみんなよく躾けられていた。下男や下女を笞で殴ることはNGで、召使いの童子や小女を、自分の子どもや娘にように見ていたのがよくわかった。
ある時、言ったことをしてくれないから、自分より幼い童子を怒鳴りつけたことがあった。
そうしたら、おふくろに叱られたんじゃ。
貴賤雖殊、人則一也。汝如是大時、能為此事否。
貴賤殊なれりといえども、人なることはすなわち一なり。汝、かくの如きの大の時、よくこの事を為せるや否や。
「主人と下僕で身分が違うと思っているのか知らないけど、同じ人間なんだからね。あなたがこの子の年齢の時、あなたは言われたとおりに出来たんですか!」
むむむ。
先公凡有所怒、必為之寛懈。唯諸児有過、則不掩也。
先公およそ怒るところ有れば、必ずこれが為に寛懈す。ただ、諸児に過ち有れば、すなわち掩わず。
死んだおやじは怒ると手がつけられなかったが、そんな時はいつもおふくろはいろいろとりなしていた。しかし、子どもらが何か間違ったことを仕出かした時は、絶対に黙っておいてくれなかった。
おやじにチクるのだ。わしも何度かチクられたことがあったが、そんなとき、おふくろはいつも言っていた、
子之所以不肖者由母掩其過、而父不知也。
子の不肖なる所以は、母のその過ちを掩いて、父の知らざるによるなり。
「子どもがダメになってしまう理由は、母親が我が子かわいさに子どもの間違いを隠してしまい、父親がそのことを知らないので、結果、怒るタイミングを失ってしまうことによるのだよ」
うーん、むむむ。
夫人男子六人、所存惟二。於教之之道、不少暇也。
夫人男子六人あるも、存するところはただ二のみ。これを教うるの道において、少しくも暇せず。
おふくろには男の子だけで六人息子がいたのだが、結局大人になったのは、わしと兄貴の二人だけだ。しかし、わしら子どもを教え導くということについては、まったく弛まなかった。
わしがまだほんとによちよち歩きのころ、
纔数歳、行而或踣。
纔か数歳、行きて或いは踣(たお)る。
まだ二歳か三歳、歩いていてしばしば倒れた。
当たり前だよね。すると、
家人走前扶抱、恐其驚啼。
家人前に走りて扶抱し、その驚き啼くを恐る。
下男下女はわしの前に走ってきて助け起こし、抱っこして、びっくりして泣き出さないようにしてくれた。
ところが、
夫人未嘗不呵責。曰、汝若安徐、寧至踣乎。
夫人、いまだ嘗て呵責せずんばあらず。曰く、汝もし安んじて徐ろなれば、なんぞ踣るるに至らんや。
おふくろのやつは、いつも呵責(仏教用語では「かしゃく」ですが、ここは「かせき」と読んでください)して𠮟りつるのだった。そして、
「あなたにはいつも言っているでしょう、ゆっくり歩きなさい、て。ゆっくり歩いていれば倒れることなどなかったはずよ」
というのだ。
むむむ。
また、
嘗食絮羹、皆叱止之。
つねに食らうに、羹(こう)を絮(じょ)すれば、みな叱りてこれを止どむ。
食事の時は、いつも、スープを(箸で)かきまぜると、そんなことをするなと叱られたものだ。
スープをかき混ぜること自体は無作法なことではない。だが、おふくろに言わせれば、
「スープをかき混ぜるのは、味の偏りを無くして味をよくしようとすることです。
幼求称欲、長当何如。
幼きより欲に称(かな)わんことを求むれば。長じて何如(いかん)ぞ。
小さいときから欲望をかなえようとばかりしていては、大人になってからどんな人になってしまうことでしょうね」
なので、スープを美味くする工夫をしていはいけない、というのであった。
与人争忿、雖直不右。
人と忿(いか)りを争うに、直といえども右(たす)けず。
誰かと怒って言い争っていると、こちらに分があることでも、おふくろは味方してくれなかった。
言うことには、
「正しいことでも通らないことはよくあります。
患其不能屈、不患其不能伸。
その屈する能わざるを患う、そのよく伸びんことを患えず。
あなたがガマンすることができない子どもになるのが心配だから味方しないんです。あなたが勝ち誇ることができない人に成長しても、なんにも心配することはないんですからね」
故兄弟、平生於飲食衣服無所択、不能悪言罵人。
故に兄弟、平生に飲食衣服に択ぶところ無く、悪言罵人するあたわざるなり。
このせいで、おれと兄貴は、成長してからも飲み物食べ物、着るものに文句は一切無く、また人のことを悪く言ったり𠮟りつけたりすることができなくなってしまった。
(伊川先生は相当ひとにぼろくそ言いますが・・・)
ほんとにもう・・・、でも、いずれにしろ、
其慈愛可謂至矣。
その慈愛は至れりと謂いつべし。
おふくろにはずいぶん愛情を込めて育ててもらった、とは言うべきだけどね・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・
「近思録」巻六・斉家篇より。伊川先生の話だから、ゴリゴリの理詰めの理想論か、と思いましたが、おふくろの思い出話はさすがにゴリゴリではありませんでした。当時の士大夫の家庭の、もちろん恵まれた階層なんですが、意外と人間的なのが垣間見えるようではありませんか。子どものころは「うっせいわ!」だったかも知れませんが、この話をしているときは、もう兄貴の程明道先生も死んだあとです。親に文句は言えません。文句を言えばそのまま自分の子どもや孫から還ってくるんです。